看護師国家試験対策講座
合格システム
よく当たります!的中問題公開!!
国試受験生、講師、編集…みんなの力が終結した結果です

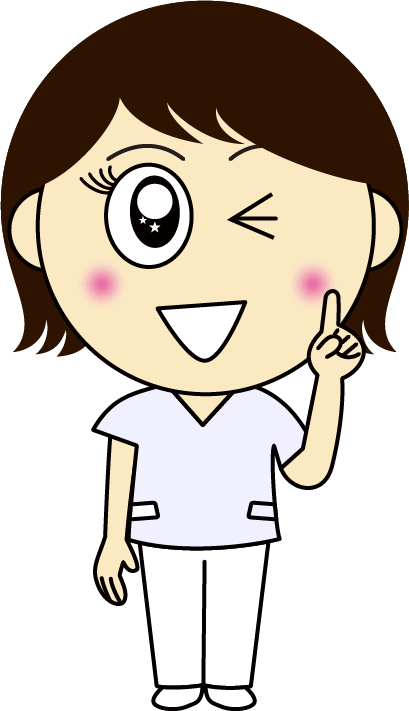 模擬試験、テキストで使用される問題が本試験でも多数出題(類似問題)されています。長年、本試験問題を収集し、本試験の正答率では受験生のみなさんに協力いただき、講師、編集者がしっかり分析を重ねた結果の答えだと自負しています。これは当社の自慢のひとつでもあります。
模擬試験、テキストで使用される問題が本試験でも多数出題(類似問題)されています。長年、本試験問題を収集し、本試験の正答率では受験生のみなさんに協力いただき、講師、編集者がしっかり分析を重ねた結果の答えだと自負しています。これは当社の自慢のひとつでもあります。
では、これから国試合格を目指すみなさんに的中問題を紹介いたします。ほぼ、同じ問題から問われ方が異なるだけの問題、解答の選択肢が同内容の問題…と様々な形態で的中が見られます。「あっ、ほとんど同じだ!」「なかなかやるじゃん」など、色々なご感想があるかと思いますが、ひとつ楽しんでご覧ください。
最後に、東京アカデミーでは的中問題を多く含むテキストを使用して教室対面式の通学講座やオンライン講座、短期講習を開講しています。きっと、各試験合格への早道になると思いますので、気になる講座のWEBページをご覧ください。
第114回看護師国家試験
午前問題1
日本の令和4年(2022年)の生産年齢人口の構成割合に最も近いのはどれか。
- 1.40%
- 2.50%
- 3.60%
- 4.70%
科目別強化テキスト<社会保障> 問題1
日本の令和4年(2022年)における年齢別人口について正しいのはどれか。
- 1.年少人口割合は、約20%である。
- 2.生産年齢人口割合は、約60%である。
- 3.老年人口割合は、約40%である。
- 4.従属人口指数は、低下傾向にある。
午前問題12
成人の食道の構造で正しいのはどれか。
- 1.胃の幽門につながる。
- 2.上1/3が平滑筋である。
- 3.生理的狭窄部位がある。
- 4.長さは約45cmである。
アラカルト<人体> 問題26
次の文中の①、②に入る数値の組合せとして正しいのはどれか。
食道は、長さ約( ① )cmの管状の臓器であり、( ② )箇所の生理的狭窄部位がある。
- 1.①15 ②2
- 2.①15 ②3
- 3.①25 ②2
- 4.①25 ②3
午前問題19
骨盤底筋訓練が有効な尿失禁はどれか。
- 1.溢流性尿失禁
- 2.機能性尿失禁
- 3.切迫性尿失禁
- 4.腹圧性尿失禁
第3回全国公開模試 午前問題18
腹圧性尿失禁への対処で行う筋力トレーニングの部位で最も適切なのはどれか。
- 1.大胸筋
- 2.上腕二頭筋
- 3.大腿四頭筋
- 4.骨盤底筋
午前問題59
ポリファーマシーの説明で正しいのはどれか。
- 1.医療者の指示通りに服薬しない状況
- 2.多剤併用による有害な事象が生じている状態
- 3.認知機能の低下により服薬管理が困難な状態
- 4.処方されている薬の内容を理解していない状況
予想問題テキスト② 問題66
ポリファーマシーの説明で適切なのはどれか。
- 1.多くの薬を服用することで副作用〈有害事象〉が生じることである。
- 2.終末期に自分がどのような医療を受けたいかをあらかじめ文書で示しておくことである。
- 3.医師の指示通りに処方された薬を服用することである。
- 4.患者自身が治療方針に納得した上で治療に積極的に参加することである。
午前問題67
正期産の時期のノンストレステスト〈NST〉で正常なのはどれか。
- 1.20分に2回以上の一過性頻脈がある。
- 2.胎児心拍数基線が80bpmである。
- 3.基線細変動が5bpmである。
- 4.一過性徐脈がある。
第1回全国公開模試 午前問題105
NST〈non-stress test〉を実施し、胎児の状態は良好であると判断した。
この判断に満たない条件はどれか。
- 1.胎児心拍数基線が140bpmであった。
- 2.胎児心拍数基線細変動があった。
- 3.20分間に2回の一過性頻脈が認められた。
- 4.1回の早発性一過性徐脈が認められた。
午前問題105
入院2週、Aさんは自宅への退院を目指し、回復期リハビリテーション病棟へ転棟することになった。Aさんは、座位姿勢での右側への傾きが徐々に改善され、食事や作業療法の時間は車椅子での座位保持が可能になってきた。Aさんは看護師の介助で車椅子に移乗が可能となり、車椅子でトイレに移動できるようになった。看護師はAさんのADLの拡大を目標に、看護計画を修正することにした。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準における評価で、Aさんの生活状況はどれか。
- 1.ランクJ
- 2.ランクA
- 3.ランクB
- 4.ランクC
予想問題テキスト② 問題116
民生委員と共に地域包括支援センターの看護師がAさんの自宅を訪問した。Aさんは、 常時臥床した状態で坐位もとれなくなっていた。意識レベルに問題はみられず、Aさんは「主人に迷惑をかけて申し訳ない。」と話している。
Aさんの障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクはどれか。
- 1.ランクA
- 2.ランクB
- 3.ランクC
- 4.ランクJ
午後問題1
日本の令和4年(2022年)の人口動態統計で、女性の死亡数が最も多い悪性新生物〈腫瘍〉の発生部位はどれか。
- 1.肺
- 2.子宮
- 3.大腸
- 4.乳房
ザ・ファイナル問題集 P11
☆文章の内容が正しければ〇、誤りがあれば×を( )に記入してください。
( )令和4年(2022年)の人口動態統計において、死因順位の第1位は悪性新生物であり、男性では胃がん、女性では大腸がんによる死亡が最も多い。
午後問題13
臓器の移植に関する法律において脳死の判定基準となっている検査はどれか。
- 1.脳波検査
- 2.筋電図検査
- 3.神経伝導検査
- 4.脳脊髄液検査
第1回全国公開模試 午前問題10
脳死判定に必要な検査はどれか。
- 1.聴覚検査
- 2.心電図検査
- 3.脳波検査
- 4.筋電図検査
午後問題44
地域包括ケアシステムの構成要素はどれか。
- 1.交通
- 2.雇用
- 3.情報
- 4.住まい
ザ・ファイナル問題集 P10
☆文章の内容が正しければ〇、誤りがあれば×を( )に記入してください。
( )地域包括ケアシステムの5つの構成要素は、介護、医療、予防、住まい、生活支援・福祉サービスである。
午後問題68
精神障害のある人のリカバリーで正しいのはどれか。
- 1.症状の回復がゴールである。
- 2.直線的なプロセスをたどる。
- 3.主体的に人生を新たに生き直すことである。
- 4.ストレス脆弱性に焦点を当てた支援である。
第3回全国全国模試 午前問題65
精神障害者のリカバリ〈回復〉で正しいのはどれか。
- 1.医学的な回復のみを目的にしたものである。
- 2.自身の力を十分に発揮するための支援である。
- 3.医療者が主体的に関わることが重要である。
- 4.具体的な生活上の問題に着目する支援である。
午後問題90
身長160cm、体重60kgの成人の体格指数〈BMI〉を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。
解答:① ② . ③
- ① 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- ② 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- ③ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第2回全国公開模試 午後問題90
身長160cm、体重60kgの成人の体格指数〈BMI〉を求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:① ②
- ① 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- ② 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
