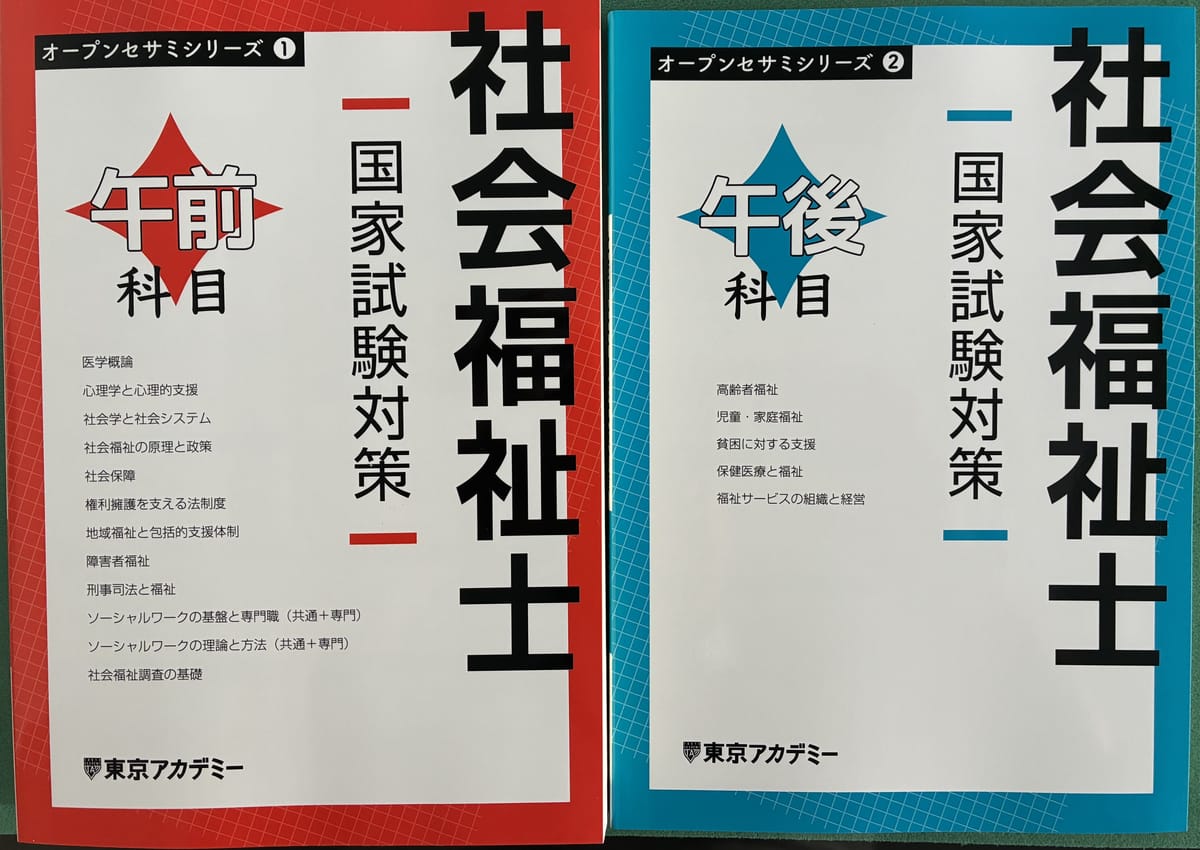東京アカデミー東京校
ブログ
社会福祉士国家試験・試験科目について⑪「ソーシャルワークの理論と方法」
こんにちは!社会福祉士国家試験対策の予備校=東京アカデミー東京校の社会福祉士国家試験担当です。
科目ごとに、どのような科目であるか、難易度はどうか?などを説明していますが、今回は、「ソーシャルワークの理論と方法」です。
その概要、難易度、そして効果的な対策について、過去問分析を踏まえて詳しく解説していきます。
「ソーシャルワークの理論と方法」とは?実践に繋がる知識と技術を学ぶ
「ソーシャルワークの理論と方法」は、
社会福祉士が個人、家族、集団、地域社会といった多様な対象に対して、
具体的な支援を展開するために必要となる主要なソーシャルワーク理論と、それに基づいた援助技術を理解するための科目です。
具体的には、個人援助技術(ケースワーク)、集団援助技術(グループワーク)、地域援助技術(コミュニティワーク)、
ソーシャルワークにおけるアセスメント、計画、介入、評価のプロセス、記録、多職種連携、倫理的課題への対応などが含まれます。
社会福祉士は、様々な理論を理解し、それぞれの状況に応じて適切な援助技術を選択し、効果的な支援を提供することが求められます。
この科目は、ソーシャルワーク実践の中核となる知識と技術を習得するために非常に重要です。
「ソーシャルワークの理論と方法」の難易度分析:過去問からの考察
過去の社会福祉士国家試験問題を分析すると、「ソーシャルワークの理論と方法」の難易度はやや高めと評価できます。その理由として、以下の点が挙げられます。
- 多様な理論と技術の理解: ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークといった主要な援助技術に加え、それぞれの理論的背景や具体的な展開方法を理解する必要があります。
- 援助プロセス全体の理解: アセスメントから評価に至る援助のプロセス全体を段階的に理解し、それぞれの段階における社会福祉士の役割を把握する必要があります。
- 事例問題への応用力: 理論や技術に関する知識だけでなく、具体的な事例を通して、どの理論に基づいたどのような援助技術を用いるべきかを判断する応用力が問われます。
- 多職種連携と倫理的課題への対応: 複雑化する現代の社会福祉課題に対応するため、多職種との連携の重要性や、ソーシャルワーク実践における倫理的課題への対応も問われます。
- 抽象的な概念の実践への落とし込み: 理論や原則といった抽象的な概念を、具体的な援助場面でどのように実践していくかを理解する必要があります。
過去問を詳細に分析すると、
ケースワークの展開過程(インテーク、アセスメント、計画、介入、終結、評価)、
代表的なケースワーク理論(心理社会的アプローチ、機能的アプローチ、課題中心アプローチなど)、
グループワークの展開過程と技法、
コミュニティワークの展開過程と技法、
ソーシャルワークにおけるアセスメントの種類と方法、
記録の重要性と種類、
多職種連携の意義と実際、
ソーシャルワークにおける倫理的課題といったテーマに関する出題頻度が高い傾向にあります。
近年では、ナラティブアプローチ、ストレングス視点の実践、危機介入、トラウマインフォームドケアなども重要なテーマとして問われています。
効果的な対策:過去問分析に基づいた学習法
「ソーシャルワークの理論と方法」を攻略するためには、
各援助技術の理論的背景と具体的な展開方法を理解し、事例問題を通して実践的な応用力を養うことが重要です。
- 主要な援助技術の理論と展開方法の体系的な理解: ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークそれぞれの目的、理論的背景、展開過程、具体的な技法、留意点などを整理して理解しましょう。
- 援助プロセス全体の段階的な理解: アセスメント、計画、介入、評価といった援助の各段階における社会福祉士の役割、用いられる技術、留意点などを理解しましょう。
- 事例問題への積極的な取り組み: 過去問や模擬試験の事例問題を積極的に解き、事例の状況を分析し、適切な理論と援助技術を選択する練習を重ねましょう。解答の根拠を明確にすることが重要です。
- 基本用語の正確な理解: ソーシャルワークには多くの専門用語が登場します。曖昧な理解ではなく、正確な意味を理解し、使えるようにしましょう。
- 多職種連携の実際を学ぶ: 保健、医療、教育、司法など、多様な分野との連携の目的、方法、留意点などを理解しましょう。
- 倫理的課題への対応力を養う: ソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマの事例を通して、倫理原則に基づいた適切な判断プロセスを理解しましょう。
- 関連科目の知識との連携: 「ソーシャルワークの基盤と専門職」で学んだ理念や価値を土台として、他の専門科目の知識と関連付けながら学習することで、より深い理解につながります。
まとめ
「ソーシャルワークの理論と方法」は、社会福祉士として実践活動を行う上で最も重要な科目の一つです。
多様な理論と技術を理解し、事例問題を通して応用力を高めることで、効果的な支援を提供できる専門職を目指しましょう。
過去問分析に基づいた効果的な学習法を実践し、社会福祉士国家試験合格に向けて着実に歩みを進めてください。
東京アカデミー東京校では、
過去問を徹底的に分析し、
合格に必要な知識を効率的に学べるカリキュラムを提供しています。
ぜひ、東京アカデミー東京校のオンライン講座を活用して、
社会福祉士国家試験合格への第一歩を踏み出してください。
皆様の合格を心より応援しています!